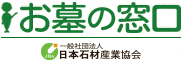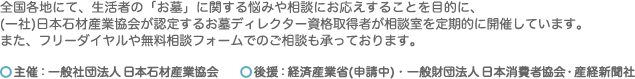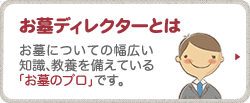はかまどトピックス
2016/09/23
墓石の産地のおはなし<茨城編>

<茨城県産真壁石>
真壁石は、筑波山から北に15kmほどのところに位置する茨城県西部の桜川市真壁町の加波山から採掘されます。
他の数多くの石材と同じ”花崗岩”と呼ばれる石種にあたり、ここ桜川市、笠間市周辺では良質な石材が豊富に採掘されることから「花崗岩の国内三大採石地」と言われています。
古く鎌倉時代からこの地域では、真壁で採れた石を使い職人たちが灯籠、石仏、墓石、石工芸品など腕を競い合い多くの職人が育ちました。技術が発展し匠の技が高く評価され、真壁石燈籠は経済産業大臣指定の伝統工芸品に指定されるほどになりました。
良質な石が採掘されるからこそ良い腕の職人がここ真壁に育ちました。
明治期に、東京では皇居の近隣で近代建築を取り入れ、近代化都市計画の動きが活発になり、ドイツやイギリスなど西洋から建築の知識や技術を取り入れるようになりました。
そんな中で、当時、近代建築に必要な良質な石材が関東周辺にはなく、政府は国勢調査を行い、その調査で見つかったのが、茨城県西部に位置する真壁石なのです。
固く丈夫で美しい良質な真壁石は、たちまち、迎賓館、日本銀行、東京商工会議所、司法省などの多くの建物に使用されました。
それをきっかけに、真壁石は大々的に採掘されるようになり、首都圏へ石を運ぶ手段として鉄道が開通されたほどです。
茨城県を代表する国産石材であり、日本の近代建築を支えた石でもあるのです。