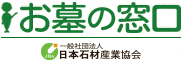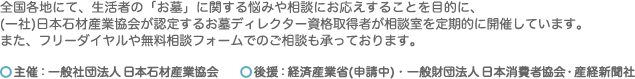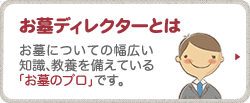はかまどトピックス
2016/07/01
お盆にお墓参りをする意味とは?

これからお盆にかけて、お墓参りをしようと思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで、なぜ「お盆」にお墓参りをするようになったのか、その意味について学んでみましょう。
そもそも「お盆」の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんへえ)」といいます。
盂蘭盆(うらぼん)はサンスクリット語の「ウランパナ」を音写(サンスクリット語の音をそのまま漢字にあてはめて読まれた言葉)で「倒懸(とうけん)」と意訳されます。
「倒懸」とは逆さ吊りにされるような、耐えがたい苦しみのことで、地獄や餓鬼道(食べ物がなくて飢えに苦しむ世界)などの悪処に落ちて、苦しみを受けている死者を救うための法会(ほうえ)なのです。
『仏説盂蘭盆会経(中国で作られたインドの経典に似せて作った経典)』には、次のようなお盆の起源に関する話が述べられています。
お釈迦様の弟子の目蓮(もくれん)は、若くして母親を亡くしましたが、その母親が餓鬼道に落ちて苦しんでいることを知り、お釈迦様に母親を救う教えを請いました。
その教えに従って、僧院にこもって修行し終えた僧侶たちにご馳走を供養したところ、母が餓鬼道から救われたといいます。この出来事にちなんで、「盂蘭盆会」が行われるようになりました。
しかし、中国では『仏説盂蘭盆会経』により盂蘭盆会が一般に普及し、後に本来の意味が転じて先祖の霊を供養する行事へと変化しました。これが日本に伝えられて「お盆」の行事になったといわれています。
日本で最初にお盆の法要が営まれたのは推古天皇の14(606)年と伝えられ、奈良時代以降は毎年7月15日に宮中で行われるようになりました。
鎌倉時代になると庶民の間でも普及しはじめ、室町時代には京都の「大文字焼き」に代表されるような迎え火や送り火といった風習があらわれ、精霊流し(しょうろうながし)などを行うようになります。江戸時代には盂蘭盆会は庶民の間でも広まり、家庭でも精霊棚を設けて、先祖を祀り、盆提灯をかざるようになりました。またこの頃には檀家制度が確立し、寺院と檀家との関係が密接になったことから、僧侶が家々をまわって「棚経(精霊棚の前で行う読経)」をあげるようになりました。
しかし、日本には古くから先祖の霊を敬う祖霊信仰があり、各地で行われているお祭りも祖霊祭を中心としたものが多くあります、これに仏教の思想や行事など加味して独立させたのが、現在の「お盆」のスタイルになったといえるでしょう。
みなさまにも、古来から受け継がれる日本の行事「お盆」を大切にし、ご先祖様を敬い、供養する習慣を忘れないでいただければと思います。
広報委員会 大代賢太郎